 飛鳥
飛鳥 横浜港
横浜港●第1回(2001 1.22) 日本に客船は5隻しかいない
●第2回(2001 1.27) 船に揚がっている旗の意味は?
●第3回(2001 2. 3) 揺れない船はない
●第4回(2001 2.10) 船体に書いてある記号は何?
●第5回(2001 2.17) 港にある電光掲示の意味は?
●第6回(2001 2.24) 船は安全な乗り物
●第7回(2001 3. 3) 船はどこを走ってもいいのか
●第8回(2001 3.10) ブリッジにお邪魔してみよう
●第9回(2001 3.17) 船と飛行機の共通点・相違点
●第10回(2001 3.24) 気軽に船に乗ってみよう
●日本に客船は5隻しかいない 第1回(2001 1.22)
海洋国ニッポンには沢山の船がありますが、一般人が乗れる船はフェリー/定期船、レストラン船/遊覧船、客船に分かれます。フェリーと定期船はA地点からB地点への交通手段で、車が積めるものをフェリー、人や荷物だけが乗る船を定期船(または旅客船)と呼び、日本には200隻ほどあります。
客船(クルーズ客船とも言う)は外見はフェリーと似ていますが、目的が全く違い、船で楽しい時間を過ごすためにあります。ホテルかレジャー施設が海に浮かんでいるようなものです。現在日本にあるのは、「にっぽん丸」「ふじ丸」「飛鳥」「おりえんとびいなす」「ぱしふぃっくびいなす」の5隻だけ。5隻とも大きさは2万t強で、日本近海のあちこちを不定期に走っています。比較的遭遇しやすいのは、東京、横浜、神戸、大阪港に停泊している時です。
 飛鳥
飛鳥 横浜港
横浜港
●船に揚がっている旗の意味は? 第2回(2001 1.27)
港に停泊中の船のブリッジ上を見ると、青地に白い四角の旗が揚がっています。これはアルファベットのP旗で「本船は24時間以内に出港する」という意味です。 港を出てからよく見るのは、黄色と青の縦縞のG旗「Pilot(水先案内人)を求む」というもの。Pilotが小型船を横付けて縄ばしごで乗船した後は、左半分が白で右が赤のH旗「本船にはPilotが乗船している」に変わります。1枚だけでなく3枚ほど組み合わせ「本船は○○港に入港する」と示すのにも使います。 出港する船に対してUとWの旗を揚げると「貴船がよい航海に恵まれますように」というお見送りの意味。 UW旗は船具店などで買えますので、客船の出港に持っていくと船から返事として「UW1」旗を揚げてもらうことができます。


ふじ丸UW1旗 UW旗 とでんたさん
●揺れない船はない 第3回(2001 2.3)
最近の船には横揺れ防止装置があるので揺れないという宣伝を聞きますが、下が水である以上、揺れを完全に防ぐことはできません。 揺れには次の6種類があります。
<船の重心を中心とした回転運動>
a.ローリング:左右に傾く
b.ピッチング:前後に傾く (上下動と感じる)
c.ヨーイング:船首と船尾が左右に振れる
<直線運動>
d.スウェイング:船全体が左右に動く
e.サージング:船全体が前後に動く
f.ヒーヴィング:船全体が上下に動く この中で船酔いになりやすいのはビッチングと言われています。
揺れを防ぐ装置として、水面下の外側についた魚のヒレのような部分ビルジキールと、水中に開いた翼フィンスタビライザー(発明者は日本人!)があります。これらでローリングをかなり防ぐことができます。
余談ですが、船の中のエレベーターは陸と違い、かなり揺れても動いています。

スタビライザーとビルジキール
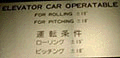
エレベータの表示
●船体に書いてある記号は何? 第4回(2001 2.10)
客船やフェリーなど大型の船の船首付近に何やら不思議なマークがあるのにお気づきでしょうか。これは、船首が球状になっていることを示すものです。水面下になりますが、船首の最前部が突起しているのを「バルパスバウ(球状船首)」と言います。これは船が前進するときに受ける水の抵抗を減らすための形です。
船首から少し後ろに行くと、水面近くに○ と十字の組み合わさった記号がついています。これは、この下に「バウスラスター」というプロペラがあることを示しています。 このプロペラは水面下、船体を貫通するトンネルの中に横向きについており、船を横移動させるのに使います。船が岸壁に着岸/離岸するとき必ず必要となるものです。
<他の文字など>
FIN:その下にフィンスタビライザーがある
TAG:タグボードを使うときにタグが着く位置
双暗車注意:「双暗車」とは2つのプロペラのこと。プロペラに気をつけよとの表示
吃水線の近くの縦の数字の並び:船底からの長さ


バルパスバウ バウスラスター
●港にある電光掲示の意味は? 第5回(2001 2.17)
東京港や横浜港には、アルファベットで電光掲示をする塔のようなものがいくつかあります。これは港への船の出入りを管制するための信号で、信号によって通航を一方にしています。意味は以下の通りです。
「I」の点滅: "IN" 入港のみしてよい
「O」の点滅: "OUT" 出港のみしてよい
「F」の点滅: "FREE"入出港とも自由
「X」「I」の交互の点灯: まもなく信号が「I」に変わる
「X」「O」の交互の点灯: まもなく信号が「O」に変わる
「X」「F」の交互の点灯: まもなく信号が「F」に変わる
「X」の点滅:まもなく信号が「X」に変わる
「X」の点灯:入出港禁止
これは、陸上の信号のように時間が来れば自動的に変わるものではなく、あらかじめ船から提出された入出港の予定をもとに、船に合わせて変えられるものです。


信号塔○ 船と信号塔○
●船は安全な乗り物 第6回(2001 2.24)
1912年のタイタニックの事故は有名ですが、これをきっかけに世界的な海上安全のためのSOLAS条約が結ばれ、多くの規則ができました。
船は、水密隔壁という壁により幾つかの区画に分けられ、万一どこかに浸水しても区画外に広がらないようにする工夫や、船底を二重にして浸水を食い止め、沈まないような仕組みになっています。
 救命いかだ
救命いかだ
船が造られるときの材料や船内で使うものは、陸上より厳しい安全基準をクリアしたものに限られます。ブリッジには、レーダー、GPS、自動衝突予防装置などコンピュータ化された総合システムが設置され、さらに人間が目視で24時間見張りをします。
 救命胴衣
救命胴衣
外航航路の客船では出航後24時間以内に乗客の避難訓練があり、一人一人が実際に救命胴衣を身に着け、自分の救命艇のそばに集合し、点呼と緊急時の説明を受けます。救命胴衣には自分の位置を知らせるための笛と電灯がついています。
グアム入港時などは米国沿岸警備隊によるさらに厳しい検査があり、乗組員の本格的な避難訓練が一日がかりで行われます。
もちろん、救命艇・救命いかだは乗客・乗組員の数以上の余裕があり、中には3日間分の水と食料、釣り道具などがあるということです。日本の客船で救命ボートを使うような事態は、まだ一度もおきていないそうです。
 救命ボート
救命ボート
●船はどこを走ってもいいのか 第7回(2001 3.3)
船は、航海資格によって走れる区域が決まっています。
・平水資格:湖、川、港内(遊覧船など)
・沿海資格:陸や島から20海里以内(フェリーなど)
・近海資格:東経175度、西経94度、南緯11度、北緯63度の線に囲まれた区域
・遠洋資格:世界中の海(日本の客船すべて)
大海原では、船はどこでも自由に走ることができます(ただし、定置網や自衛隊の演習などの区域には入れません)。
しかし出入港時や狭い水路を航行する時は、船が通る道が決められています。まず船は右側通行です。そしてブイによって示される航路内を航行します。港に入るときは、赤色のブイを右に、緑色のブイを左に見ることになります。夜も、ブイがそれぞれ独自の光を出すので、航路を確認することができます。
このような場所では、必ず陸と連絡を取り合わないとなりません。たとえば東京湾に入るときは、浦賀水道の入り口に達した時、東京湾海上交通センター(とうきょうマーチス)に位置を通報することになっています。ここが湾内をレーダーで見て船の航路管制をしたり船に必要な情報を提供してくれます。


赤のブイ 緑のブイ
船との連絡は、国際VHFを通して行われます。これは全世界共通のシステムで、船舶はチャンネル16を聴守することになっています。とうきょうマーチスと船舶との連絡も国際VHFを使っているので、CH16を聞いていれば船とのやりとりを我々も聞くことができます。
なお、CH16は遭難信号にも使うため呼出・応答のみで、話は別のチャンネルに移動してから行われます。
このような海岸局は、港湾管理機関が全国に25局(おおさかポートラジオ等)、海上保安庁が16局(おたるほあん等)、 船舶通航信号所が10局(とうきょうマーチス等)あり、すべてCH16で聞くことができます。
<ご参考>
CH16:156.8MHz
CH14:156.7MHz
CH22:161.7MHz
とうきょうマーチスの海上交通情報:1666KHz
おおさかマーチスの海上交通情報:1651KHz
●ブリッジにお邪魔してみよう 第8回(2001 3.10)
客船に乗ると、外洋を航行している間にブリッジ(操舵室)を見せてくれることがあります。 フェリーにもブリッジ見学ツアーをしてくれる船があります。そんなチャンスに巡 りあえたら、是非行って中に何があるのか見てみましょう。
 ブリッジ
ブリッジ
ブリッジに入ると、前方に見晴らしのいい窓が並び、真ん中に羅針盤と自動操舵機(オートパイロット)があるのが見えます。窓の上の様々なメーターは、プロペラの回転数と角度・舵の角度・船の左右の傾き・船のスピード・風速・風向などを示しています。
 オートパイロット
オートパイロット
船のスピードは「ノット」が単位で、1ノットは時速1852m。 18ノットだと時速33km程になります。客が乗る船では15-19ノットくらいが普通の速度で、20ノットを超えると「速いな」という感覚です。飛行機が1時間で飛ぶ距離を、船は一日かけて進みます。
再びブリッジの中に戻りましょう。ボタンや受話器がついたエンジンコントロールパネルがあり、階下にある機関室に直結しています。エンジンを担当するのは機関室ですが、ブリッジでも制御できるようになっています。
 海図
海図
大きな机には現在の海域の海図が広げられています。鉛筆で線が引いてあるのは予定航路で、1時間おきに現在位置が書き込まれます。鉛筆を使うのは、航海が終わったら消しゴムで消して別の航海に同じ海図を再び使うためです。
この他にも、レーダー、エンジンモニタリング装置、GPSなど、操縦に必要な航海計器や船内の安全を監視する装置が設置されていますが、それでもゆっくり歩き回れるスペースがあります。
操縦に直接関係ない神棚やコーヒーメーカー、鉢植えの草花があるなど、どこかアットホームな雰囲気がするのも船のブリッジです。
ここで仕事をしているのは、当直の航海士と甲板員。0-4、12-16時は二等航海士、4-8、16-20時は一等航海士、8-12、20-24時は三等航海士に会うことができます。船長も必要に応じてブリッジに出てきます。 出入港時は、ブリッジに船長と三等航海士、船首に一等航海士、船尾に二等航海士が配置され指揮を執ります。ですので映画「タイタニック」で人気になったスポットに一人で立っているのは一等航海士です。
 船首に立つ一等航海士
船首に立つ一等航海士
●船と飛行機の共通点・相違点 第9回(2001 3.17)
飛行機の世界には、船から取られたシステムが多くあります。 その中には、今でも全く同じものもあれば、違った意味をもつものもありますので、いくつかご紹介しましょう。
・航海灯(右舷は緑、左舷は赤): 夜になると飛行機の翼の両端に緑と赤のライトがつきますが、船も同じ色の航海灯をつけます。この灯りは前と横からしか見えないようになっていますので、例えば赤だけが見えたら船は向かって左へ進んでいる、両方が見えたら、船はこちらへ向かっている、と分かります。赤も緑も見えず、白い船尾灯だけ見えたなら、後ろから見ていることになります。
・左舷接岸: 飛行機の出入り口が左側というのも船からの伝統です。昔の船は港へ接岸するとき左舷で行われていたので、左舷をPortsideと呼ぶようになりました。しかし、現在は両舷とも接岸できるのが普通になり、逆に右舷を接岸することの方が多いようです。
・キャビン: 船室、おもに客室を指します。
・スチュワーデス: 飛行機の世界では使われなくなっている言葉ですが、客船ではスチュワーデス、スチュワードが活躍しています。役割は、客室の清掃・ベッドメイク・ダイニングでのサービスなどです。
・キャプテンとパイロット: 船では、キャプテンは船長であり、パイロットは水先案内人を指します。
客船や一部のフェリーの船長は、客へのサービスのために、トークショーに出たりダンスを踊ったりと、船を動かす以外の仕事が増えているようです。 パイロットは、船が出入港する際や狭い水道などを通るとき船に乗り込んできて、ブリッジで安全な航路の指示をします。
パイロットは船から独立していて、あちこちから呼ばれては小型船を横付けして船にあがり、案内が終われば帰っていきます。船長の経験があり、その港や水道に熟知したベテランです。

仕事を終えて帰っていくパイロット(縄ばしごにつかまっている人物)
●気軽に船に乗ってみよう 第10回(2001 3.24)
船の話を色々書いてきましたが、今回は実 際に船に乗るにはどうすればいいのかを紹介 したいと思います。
・とんぼ帰りフェリーの旅
いつでも気軽&身軽に乗れるのがフェリー。 上等の客室には客船並みの設備を持つものが あります。乗船時間は数時間から40-50時間 というものまで、様々な航路があります。
船に乗ったら一泊しないとつまらない、元 の場所に戻りたい、ただ船に乗りたいという 人にお勧めの一つが東京から伊豆諸島に行っ てとんぼ帰りする東海汽船のルート(関東限 定で申し訳ありません)。 東京を夜10時に出、翌朝6時に大島に着きま す。さらに利島、新島、式根島に寄り10時頃 神津島に着きます。神津島で一瞬降りてすぐ に帰りの手続きをし、船に戻ります。船は神 津島から逆に島づたいに戻ります。それぞれ に表情の違う島をゆっくり見て、東京に戻る のが夜8時。2等船室なら往復1万円かからず に伊豆諸島クルーズが味わえます。
日本にどんなフェリーがあるのか調べるに は、鉄道の時刻表の航路のページや、各船会 社のホームページを参考にされるといいと思 います。申込は、各船会社や港できます。 船によっては、季節割引や年齢割引など様々 な割引もありますので、より安く乗る方法を 探すのも楽しみです。
・客船は決して高くない
「豪華客船」という名前ばかりが広まって いる客船ですが、普通の人が乗るのはとても 簡単です。 値段は1日あたり一番安い部屋で3万〜5 万円ほど。これを高いと思う前に、その値段 に何が入っているかを見てください。交通費、 宿泊費、食費(食事は一日に6-7回)数々の イベント参加費…これら全てを陸上で支払う としたらそれ以上かかります。そして客船独 自の解放感は陸では決して味わえないもので す。だまされたと思って一度乗ってみること をお勧めします。
ところで客船はいつもどこを走っているの かといいますと、不定期にあちこちにいるの です。ワンナイトクルーズから、何箇月にも 及ぶ海外クルーズもやっています。詳細につ いては、船会社で作っているパンフレットや ホームページを見るのが便利です。最近は新 聞の広告にも出ています。 一つ一つのクルーズはパッケージ旅行のよ うなものです。どの旅がいいかを決めたら、 船会社か旅行代理店に申し込みます。申込は 余裕を持ってクルーズの1ヶ月前までに行う ことをお勧めします。 申し込んだら乗船の案内や乗船券が送られ てきますので、それを参考に旅の支度をしま す。港まで荷物を運ぶのが大変だったら宅配 便で船室まで運んでもらうことができます。 あとは乗船日に港に行けば船が待っています。
船に乗ったら、すべてが自分の自由な時間 です。イベントに出るのもよし、デッキでの んびり過ごすのもよし、日常と離れた別体験 をすることができます。お客さん同士が友達 になったり、船のスタッフと知り合えるのも、 客船ならではの特徴といえます。
日本の各客船の特徴を紹介します。
「飛鳥」(郵船クルーズ株式会社): 日本で一番大きく、豪華客船というイメージ そのまま。全船室に風呂がある唯一の船。食 事の量はふんだんで、設備が充実。船を一周 できる木の甲板が気持ちいい。ベランダ付き の部屋が多い。贅沢な気分、海外の客船に乗 った気分を求める人にお勧め。
「にっぽん丸」「ふじ丸」(商船三井客船株式会社): 戦前からずっと客船を運航してきた伝統で、 家族的な暖かいサービスをしてくれる船。食 事は最高。終日航海日はブリッジを開放し、 機関室も見学でき、船の話がたっぷり聞ける 船マニアには嬉しい船。双眼鏡を持参するお 客が多い。船好き、乗り物が好きな人にお勧め。
「おりえんとびいなす」「ぱしふぃっくびいなす」 (日本クルーズ客船株式会社): 後者は日本で一番新しい客船。2隻の内部は ほぼ同じ。スタッフが明るくフレンドリーで 気持ちがいい。値段が手ごろな上、サービス はピカ一。毎回趣向を凝らした手作りのイベ ントが人気。ブリッジ公開タイムあり。気軽 に船に乗ってみたい人、初めて船に乗る人に お勧め。

世界一周クルーズに旅立つ「ぱしふぃっくびいなす」
・よい船旅を
船に乗ったら、船からしか見られない風景 や自然の驚異が待っています。船上での珍し い体験をぜひ楽しんでいただきたいといます。 船の魅力を伝えたいと書いてきましたが、
やはり乗ってみるのが一番だと思います。
今回の連載が少しでも船への興味のお役に 立てば幸いです。
それでは船上でお会いしましょう。Bon Voyage!

「ふじ丸」から見た南鳥島(日本最東端)
著者プロフィール
本名:渋谷 晶子(しぶや あきこ)
海なし県の埼玉に生まれ育つ。中学生の時アーサー・ランサム全集(岩波書店)に出会い船に憧れる。後に横浜へ引っ越し、横浜港に係留保存されている帆船日本丸の総帆展帆(全ての帆を広げる)作業をするボランティアに参加。
1988年に会社の労働組合が中国へ船で研修旅行をする「青春の船」というイベントを企画。それに参加して初めて船に乗り(新さくら丸)、感動のあまり半分自費で本を出版。イラストレーターの柳原良平先生に挿し絵を描いていただく。
これ以降、本格的に船にハマり、日本の客船はすべて制覇。セイルトレーニング用の帆船「海星」にスペインで乗船。船に乗った回数は、帆船、客船、フェリー合わせて40回程。日本の客船がメインだが、種類を問わず、これからも沢山の船に乗っていきたい。
このお正月は日本最東端の南鳥島まで行くクルーズに参加し、日本で一番早い初日の出を拝む。周囲何百キロも陸のない絶海の孤島を一周し、真夏の日差しを浴びて、日本の広さを実感した。
著書:「時間(とき)の流れは17ノット」
東京経済 小林晶子著 1989年